ソイプロテインは痩せる?5つのダイエット効果と活用方法を紹介
- 公開日
- 2025年02月21日
- 更新日

ソイプロテインは、低カロリー・低脂肪でありながら、タンパク質をしっかり補給できるためダイエットにおすすめです。
近年の研究では、ソイプロテインが満腹感を持続させることで食べ過ぎを防ぎ、カロリー摂取量を自然に抑える効果が示唆されています。さらに、コレステロール値を低下させる効果や、脂肪の燃焼を促進する効果についても研究が進められており、ダイエットだけでなく健康管理にも役立つと考えられています。
本記事では、ソイプロテインがダイエットに与える具体的な影響や、その科学的根拠を詳しく解説します。また、ソイプロテインを活用したダイエット方法として、手軽に取り組める「置き換えダイエット」についても紹介します。
ソイプロテインの効果や活用法を学び、健康的な体づくりに活かしましょう。
ソイプロテインを使うと痩せる?

ソイプロテイン(大豆由来のプロテインパウダー)は、ダイエットをサポートする食品として注目されています。近年の研究では、ソイプロテインの摂取により、体脂肪が効率的に減少し、食事のカロリー摂取量が自然に抑えられることが示唆されています。
肥満の成人を対象に行ったある研究では、ソイプロテインのような大豆由来のタンパク質が、動物性タンパク質よりも効率的に体脂肪を減少させることが示されています。(Liao et al., 2007.[リンク])
この研究では、1日の摂取カロリーを同じに設定したうえで、タンパク質の供給源のみを「大豆由来」または「動物性主体」の2つのグループに分けました。両グループは8週間にわたり、あらかじめ決められた食事プランに従って摂取を続け、体脂肪率の変化が測定されました。
その結果、大豆を主なタンパク源としたグループでは、体脂肪率が平均2.2%減少しました。一方、動物性タンパク質中心のグループでは、1.4%の減少にとどまりました。
- 大豆を唯一のタンパク源としたグループ:2.2%
- 動物性タンパク質を中心としたグループ:1.4%
つまり、同じカロリー制限を行った場合でも、大豆タンパクを摂取することで、より効果的に体脂肪を減らせる可能性があることが示唆されました。
また、ソイプロテインには食事全体のカロリー摂取量を減らす効果があることも別の研究によって示されています。(Takahashi et al., 2024.[リンク])
12週間にわたる別の研究では、プラセボ(タンパク質を含まないドリンク)グループのカロリー摂取量が1日あたり平均121kcal減少したのに対し、ソイプロテインを摂取したグループでは340kcal減少しました。
この傾向は、同時に検証されたホエイプロテイン摂取グループよりも顕著であり、ソイプロテインは満腹感を高め、自然と食事量を抑える効果が高いことが示唆されました。
これらの研究結果から、ソイプロテインの摂取は体脂肪の減少と食事のコントロールに有益であると考えられます。
ソイプロテインがダイエットに寄与する5つの効果

ソイプロテインには、ダイエットをサポートするさまざまな働きが期待できます。ソイプロテインに含まれる大豆タンパク質やイソフラボンには、満腹感の持続や脂肪燃焼促進などの効果があり、効率的な体重管理をサポートします。
ここからは、以下のソイプロテインがダイエットに寄与する5つの働きについて詳しく解説します。
以下、それぞれの働きが得られる仕組みやメリットについて紹介します。
1.満腹感(腹持ち)の持続
ソイプロテインのメリットの一つは、腹持ちの良さです。ソイプロテインに含まれるタンパク質は消化吸収が緩やかで、満腹感が長時間持続しやすい特徴があります。その結果、空腹を感じにくくなり、食べ過ぎや間食を抑える効果が期待できます。
実際に、朝食にソイプロテインを取り入れることで、その後の食事量が自然と減少しやすいことを示唆する研究があります。(Nepocatych et al., 2019.[リンク])
この研究では、被験者17名に対し、朝食として「ソイプロテイン」または「炭水化物主体の食事」をランダムな順序で摂取(いずれも約482kcalに調整)させ、昼食の平均摂取カロリーを比較しました。
その結果、体重1kgあたりの摂取カロリーは、炭水化物主体の食事を摂取した場合が平均11kcalであったのに対し、ソイプロテイン(50g)を摂取した場合は約9.1kcalでした。
- 炭水化物主体で摂取したグループ:約11.0kcal
- ソイプロテインを摂取したグループ:約9.1kcal
例:体重60kgの人の場合、炭水化物グループでは660kcalに対して、ソイプロテイングループでは546kcalに減少したことになります。
この結果から、朝食で同じカロリーを摂取しても、ソイプロテインを摂ることで満腹感が持続し、その後の昼食の摂取カロリーが抑えられることが示唆されました。
2.体脂肪の燃焼促進

ソイプロテインに含まれるイソフラボンには、脂肪燃焼を助ける働きがあります。
イソフラボンによる脂肪燃焼には、アディポネクチンというホルモンが関与しています。アディポネクチンは、イソフラボンの摂取により分泌が増加し、脂肪の燃焼を促進する働きがあります。
この仕組みは、実際の研究においても支持されています。(Sato et al., 2007.[リンク])
肥満体型の日本人女性21人を対象に、イソフラボンを8週間摂取したグループと、摂取しなかったグループを比較した研究が行われました。
その結果、イソフラボンを摂取したグループは、アディポネクチンの分泌が増加し、内臓脂肪が7.5%減少したことが確認されています。以上の研究から、イソフラボンの摂取は、アディポネクチンの増加を介して脂肪の燃焼を助けることが示唆されました。
3.便秘解消
ソイプロテインには、大豆由来の食物繊維が豊富に含まれており、腸内環境の改善をサポートします。特に多く含まれる不溶性食物繊維は、腸のぜん動運動を活発にし、老廃物の排出を促すため、便秘解消に役立ちます。
腸の健康と代謝は密接に関係しており、便秘が続くと代謝が低下し、脂肪の燃焼効率が落ちてしまいます。
便秘が解消されると、腸内の善玉菌が増え、悪玉菌の繁殖が抑えられます。その結果、腸内環境が整い、むくみや血行不良の改善につながります。さらに、腸内環境が整うことで、消化・吸収がスムーズになり、代謝が向上し、脂肪が燃えやすい体質へと変化します。
4.コレステロール値の低下
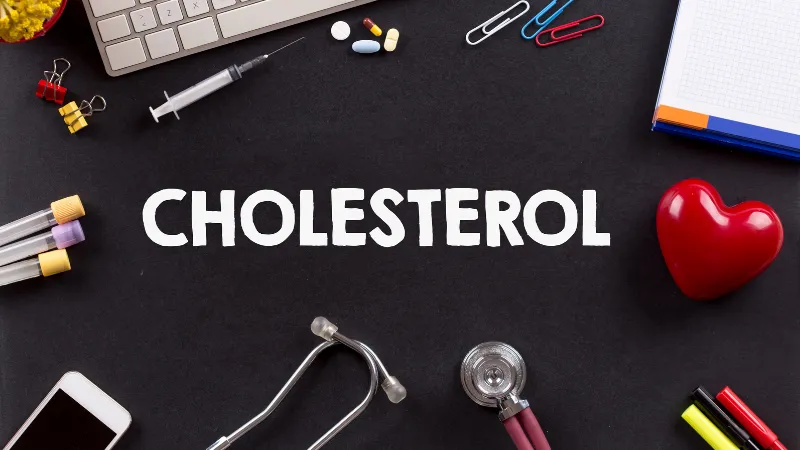
ソイプロテインに含まれるタンパク質には、コレステロールの吸収を抑える作用があります。腸内でコレステロールの吸収に関与する胆汁酸と結びつき、体外へ排出されることで、血中コレステロール値の低下が期待できます。
大豆タンパク質の摂取が血中脂質に与える影響に関する研究では、総コレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪の減少が確認されています。(Anderson et al., 1995.[リンク])
一方で、血管内に蓄積した余分なコレステロールを回収する、HDLコレステロール(善玉コレステロールとも呼ばれる)は影響を受けなかったことから、血中脂質の改善が期待できます。
さらに、ソイプロテインはコレステロールを含まないため、動物性タンパク質の代わりに取り入れることで、脂質の摂取を効果的に抑えられます。
5.筋肉量の維持・増加
ソイプロテインに含まれるタンパク質は、筋肉の材料となる重要な栄養素です。筋肉は基礎代謝の大部分を担っており、筋肉量が増えることで基礎代謝が向上し、痩せやすい体質になります。
ダイエット効果を高めるためには、ソイプロテインを摂取する前後に筋トレを取り入れるのがおすすめです。これにより、筋肉量が増えて基礎代謝が向上し、消費エネルギーも増えるため、より効果的なダイエットが期待できます。
また、ホエイプロテインに比べて筋肉を増やす効果が弱いと言われることがありますが、それは誤解です。確かにホエイプロテインと比べると消化吸収は緩やかですが、筋肉を作るのに欠かせないアミノ酸スコアは高いです。実際にソイプロテインにはホエイプロテインと同等の筋力増強効果があることが示された研究データもあります。
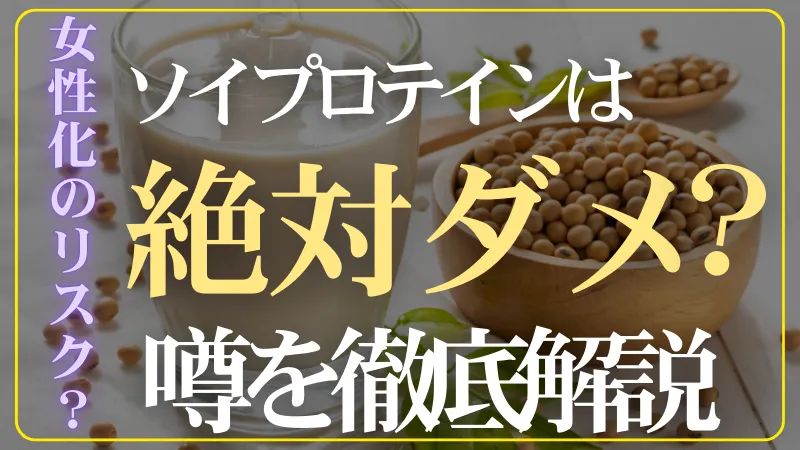
「ソイプロテインは絶対ダメ」は嘘?女性化や筋肉への影響などの真相
ソイプロテインには「女性化する」「筋肉がつかない」といった噂がありますが、それらは誤解です。その根拠となる理由を徹底解説します。
ダイエット以外にも期待できる美容効果

ソイプロテインに含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た働きを持ち、体内でさまざまな美容効果をもたらします。エストロゲンの減少は肌のハリ低下や髪のパサつきにつながりますが、ソイプロテインを摂取することで、エストロゲン様作用を補い、美容と健康の維持に役立ちます。
- 美肌効果
- コラーゲンやヒアルロン酸の生成を促進し、肌のうるおいと弾力を向上
- アンチエイジング
- 抗酸化作用により、紫外線やストレスによる肌の老化を防ぐ
- シミ・くすみの予防
- メラニンの生成を抑え、シミやくすみの発生を軽減
- 髪や爪の健康維持
- エストロゲン様作用が、髪のツヤや爪の強度を向上
- ホルモンバランスの調整
- エストロゲンの働きをサポートし、生理前の肌荒れや体調不良を軽減
これらの効果を得るためには、継続的にソイプロテインを摂取し、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。美容と健康の両方をサポートする食品として、ソイプロテインを上手に取り入れましょう。
ソイプロテインを活用したダイエット方法

ソイプロテインダイエットは、どの方法を選択するかによって、削減できるカロリーやメリット・デメリットが異なります。無理なく継続するためには、自分のライフスタイルに合わせた方法を選択することが大切です。
ソイプロテインを活用したダイエットには、主に以下の3つの方法があります。
ここからは、それぞれのダイエット方法のメリットや注意点について解説します。
3食のうち1食をソイプロテインに置き換える
効率的にダイエットを進めたい方には、1日3食のうち1食をソイプロテインに置き換える方法がおすすめです。この方法では、必要なタンパク質を確保しつつ、摂取カロリーを大幅に抑えられます。
例えば、普段1日2,100kcalの食事を摂っている場合、1食分(700kcal)をソイプロテイン(約120kcal)に置き換えることで、1日あたり約580kcalの削減が可能です。
1食を置き換えるタイミングとしては、夕食がおすすめです。夜は脂質の多い食事を摂る傾向があり、活動量も低下するため、摂取したエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなります。そこで、低カロリーなソイプロテインに置き換えることで、効率的なカロリーコントロールが可能になります。
ただし、ソイプロテインだけではビタミンやミネラルが不足しやすいため、残りの2食で栄養バランスを意識することが重要です。野菜や果物、ナッツ類を積極的に取り入れ、健康的にダイエットを進めましょう。
3食のうち1食の主食をソイプロテインに置き換える
少しずつカロリーコントロールを進めたい方には、3食のうち1食の主食をソイプロテインに置き換える方法がおすすめです。
例えば、ご飯茶碗1杯(約230kcal)をソイプロテイン(約120kcal)に置き換えることで、1食あたり約110kcalの削減が可能です。
この方法のメリットは、極端な食事制限をせずに、無理なくカロリーを抑えられることです。主食以外のおかずはそのまま楽しめるため、食事の満足感を保ちながら、長期的に続けやすくなります。
さらに、1食を完全に置き換える方法と比べると、栄養不足のリスクが低く、健康的にダイエットを進められます。
一方、削減できるカロリーは比較的少ないため、1食を丸ごと置き換える方法に比べると、減量効果は緩やかです。しかし、無理なく続けられるため、長期的に見ればリバウンドのリスクを抑えながら、着実に体重を管理しやすい方法といえます。
間食をソイプロテインに置き換える
普段から間食としてお菓子を食べる習慣がある方には、間食をソイプロテインに置き換える方法がおすすめです。お菓子をソイプロテインに置き換えることで、糖質や脂質の摂取を抑え、太りにくくなります。
例えば、普段から間食として食べているプリン1個(約120kcal)をソイプロテイン(約120kcal)に置き換えた場合、摂取カロリーは同じでも血糖値の安定や満腹感の持続に違いが生じます。
プリンのような甘いお菓子は糖質が多く、摂取後に血糖値が急上昇しやすいため、大量のインスリンが分泌され、その後急激に血糖値が下がることで空腹感や間食の欲求を引き起こします。
一方、ソイプロテインは糖質が少なく、消化・吸収がゆるやかで血糖値の上昇を抑えられるため、エネルギー供給が安定し、空腹感を感じにくくなります。
その結果、間食の回数や食べ過ぎを抑えやすくなり、食欲をコントロールしやすくなるというメリットが期待できます。
ただし、甘いお菓子を楽しむ機会が減るため、継続するためには自分に合った美味しいフレーバーのプロテインを選ぶことが重要です。
ダイエットにソイプロテインを利用する際の注意点

ソイプロテインは、低脂肪・低カロリーなことからダイエットに適していますが、誤った方法で利用すると、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。ソイプロテインをダイエットに利用する際には以下の3点に注意してください。
以下、それぞれの具体的な注意点について詳しく解説します。
1.過剰摂取に注意する
ソイプロテインを過剰に摂取すると、タンパク質やイソフラボンの摂取量が増えすぎて、減量や健康に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
タンパク質の摂り過ぎは、体重増加につながる可能性があります。消費しきれなかったタンパク質は脂肪として蓄えられるため、ソイプロテインの低カロリー・低脂肪というメリットが損なわれてしまいます。
さらに、タンパク質を過剰に摂取すると、腎臓や肝臓に負担をかける可能性があります。これらの臓器はタンパク質の代謝や老廃物の処理を担っているため、過剰摂取が続くと機能が低下するリスクが高まります。
大豆イソフラボンを過剰に摂取すると、ホルモンバランスが乱れる可能性があります。過剰摂取により、閉経後の女性では子宮内膜増殖症、男性では女性化乳房が報告されています。
過剰摂取を防ぐために、ソイプロテインの摂取量は1日1食までに抑えるのが望ましいです。それ以上の摂取は、食品安全委員会が定めたイソフラボンの一日摂取量の上限値である70〜75mgを超過する可能性があるため控えましょう。
また、普段から大豆食品を多く摂っている方や、大豆サプリメントを併用している方は注意が必要です。ソイプロテインを併用すると、大豆イソフラボンの摂取量が過剰になりやすいため、全体の摂取量を把握し、適切なバランスを意識することが大切です。
2.ビタミン・ミネラルを補う

置き換えダイエットなどでソイプロテインを中心とした食生活を続けると、ビタミンやミネラルが不足する恐れがあります。
ビタミンB群、マグネシウム、鉄、カルシウムなどは、エネルギー代謝や筋肉の機能維持に欠かせない栄養素です。不足すると、ダイエットや筋力維持の効果が低下するだけでなく、疲れやすくなったり、体調を崩しやすくなったりするなど、健康リスクが高まります。
そのため、ソイプロテインを活用する際は、野菜や果物、海藻、ナッツ類なども併せて摂取し、栄養バランスを意識することが大切です。また、ビタミンB群や鉄、カルシウムが配合されたプロテインを選ぶことも、有効な対策の一つです。
3.同時に運動も行う
ソイプロテインを活用したダイエットは、運動(特に筋力トレーニング)を併用することで、より効果的になります。食事制限だけでカロリーを減らすと、筋肉量が低下し、基礎代謝も落ちるため、痩せにくい体質になる可能性があります。そのため、筋トレを取り入れることで筋肉量を維持し、基礎代謝を向上させることが重要です。
ランニングやサイクリングなどの有酸素運動に加え、ヨガやピラティスといった体幹トレーニングを組み合わせることで、バランスよく筋力を向上させ、健康的に体を引き締めることができます。
ソイプロテインはダイエットにおすすめ!

ソイプロテインは、健康的に体重を管理したい方におすすめのダイエット食品です。
大豆由来の植物性タンパク質を含み、低脂肪・低カロリーでありながら、満腹感が持続しやすいのが特徴です。そのため、食べ過ぎを防ぎつつ、摂取カロリーを抑えられます。
さらに、体脂肪の燃焼促進、便秘解消、コレステロール値の低下など、ダイエットに役立つさまざまな効果が期待できます。
ソイプロテインをダイエットに取り入れる方法としては、置き換えダイエットがおすすめです。食事の一部や間食をソイプロテインに置き替えることで、効果的にカロリーコントロールを行えます。
ただし、過剰摂取には注意し、栄養バランスの取れた食事や、適度な運動と組み合わせることが重要です。ソイプロテインを上手に活用し、健康的で理想の体型を目指しましょう。

痩せる薬の通販ランキング【内科でもらえるダイエット薬】最新版
思うようなダイエット効果が得られない方におすすめの痩せる薬をピックアップ。病院のダイエット外来で処方されている成分を含む通販商品を人気ランキングで紹介。
