高血圧症の治療「薬による降圧と食事・運動療法」
高血圧症治療の基本的な流れ
高血圧症の治療は、合併症の発症や進行を防ぐことを目的として行います。
治療の対象となるのは、血圧値が140/90mmHgを超える高血圧症患者です。最新の降圧目標では130/80mmHg未満となるまで薬物治療および食事療法、運動療法を用いて治療します。
病院での診療は血圧の測定に加えて病歴の確認、視診、検診が行われます。これらをもとに、本態性高血圧または二次性高血圧のどちらか判断されます。原因が特定できない場合は、二次性高血圧が除外されます。血圧値、危険因子、合併症の有無から、3タイプの心血管病リスク群に分別して治療法を決定します。
3つの心血管病リスク群に分別されて治療法が検討されます。
下記のように、収縮期が140-159mmHgまたは拡張期が90-99mmHgの場合はⅠ度高血圧と呼ばれます。血圧値が高くなるにつれてⅡ度、Ⅲ度となります。
- Ⅰ度高血圧:140-159/90-99mmHg
- 低リスク=生活習慣の改善から治療を開始
- Ⅱ度高血圧:160-179/100-109mmHg
- 中等リスク=生活習慣の改善から治療を開始
- Ⅲ度高血圧:180/110mmHg以上
- 高リスク=直ちに降圧薬による治療を開始
心血管リスクは、Ⅰ度高血圧で「低リスク」以上、Ⅱ度高血圧で「中等リスク」以上となります。Ⅲ度高血圧では「高リスク」の可能性があり、放置すると危険な状態です。低リスク、中等リスクでは生活習慣の改善から治療を開始しますが、高リスクは直ちに降圧薬による治療を始めます。
一般的に、診察室で測った際に130/80mmHgを降圧目標として治療を行います。
糖尿病や慢性腎臓病(蛋白尿陽性)などを併発している患者でも降圧目標は同じです。ただし、75歳以上の高齢者は140/90mmHgに設定されています。
食事療法および運動療法だけでは降圧目標に達しない場合には薬物療法による治療が検討されます。
薬物療法は最も強い降圧効果が期待できる
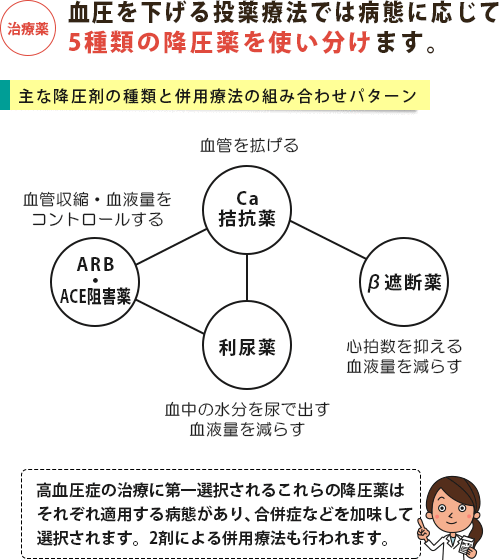
高血圧症の治療には、以下のような降圧薬が用いられます。
- カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)
- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)
- アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)
- 利尿薬
- β遮断薬
基本的に高血圧症の治療は、食事療法や運動療法による生活習慣の改善で効果が認められなかった場合に薬物療法を行います。とはいえ、多くの高血圧症患者が薬物療法を必要としているのが現状です。
薬物療法に用いられる治療薬はそれぞれ作用機序や副作用に特徴があります。症例に合わせて適切な治療薬を選択する必要があります。一般的な高血圧症にはCa拮抗薬、ARB、ACE阻害薬、利尿薬が第一選択されます。
1日1回投与の治療薬を優先的に選んで、低用量から服用を開始します。
高血圧症の治療に第一選択される薬は、主要降圧薬と呼ばれています。血圧の改善および心血管病抑制効果などが確認されています。これといった合併症がない場合には、主要降圧薬の中から使用する治療薬を決めます。
単剤では十分な効き目がみられない場合には、他の降圧薬への切り替えや併用が行われます。
薬物療法で使われる降圧薬は、糖尿病や狭心症などの疾患が併発している場合にも適応があります。例えば糖尿病を伴う高血圧症の治療には、ARBもしくはACE阻害薬が積極的適応を持っています。
| 項目 | Ca拮抗薬 | ARB ACE阻害薬 |
利尿薬 | β遮断薬 |
|---|---|---|---|---|
| 左室肥大 | 〇 | 〇 | ||
| 心不全 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 心房細動(予防) | 〇 | |||
| 頻脈 | 〇 | 〇 | ||
| 狭心症 | 〇 | 〇 | ||
| 心筋梗塞後 | 〇 | 〇 | ||
| 蛋白尿 | 〇 | |||
| 腎不全 | 〇 | 〇 | ||
| 脳血管障害慢性期 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 糖尿病/メタボリックシンドローム | 〇 | |||
| 高齢者 | 〇 | 〇 | 〇 |
カルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)は高血圧症治療に広く用いられています。
Ca拮抗薬にはノルバスク、アダラートCRなどがあります。血管を収縮させるカルシウムイオンを阻害し、血圧を改善させる働きがあります。併用例ではARB、ACE阻害薬、利尿薬のいずれかとの組み合わせが推奨されています。
左室肥大、頻脈、狭心症、慢性腎臓病(蛋白尿陰性)、脳血管障害慢性期を伴う高血圧症に積極的適応があります。徐脈や心不全などを伴う高血圧症の治療には向いていません。
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)は糖尿病を併発している場合に多く利用されます。
ARBは、日本国内ではCa拮抗薬に次いで使用頻度が高い降圧薬です。ベニテックやディオバンといった先発薬に加えてジェネリックも多く開発されています。Ca拮抗薬や利尿薬と一緒に使用することで、より強力な治療効果が得られます。
左室肥大、心不全、心筋梗塞後、慢性腎不全、脳血管障害慢性期、糖尿病、メタボリックシンドロームに積極的適応があります。妊婦や高カリウム血症の患者は使用できません。
アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)は臓器を保護する作用もあります。
コバシルなどのアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬は、昇圧物質であるアンジオテンシンⅡの生成を阻害することで高血圧症を治療します。Ca拮抗薬や利尿薬と併用することがあります。
左室肥大、心不全、心筋梗塞後、慢性腎不全、脳血管障害慢性期、糖尿病、メタボリックシンドローム、誤嚥性肺炎に積極適応があります。妊婦や血管神経性浮腫、高カリウム血症などには禁忌とされています。
利尿薬は尿を排泄することで血圧を下げます。
高血圧症の治療によく用いられるのは、サイアザイド系という種類の利尿薬になります。体内の水分や塩分の排出を促して血液量を調節することで降圧します。併用が推奨されている降圧薬はCa拮抗薬、ACE阻害薬、ARBです。
心不全や慢性腎臓病(蛋白尿陰性)、脳血管障害慢性期、骨粗しょう症に積極的な適応があります。低カリウム血症を伴う高血圧症には、サイアザイド系利尿薬は利用できませんが、アルダクトンなどのカリウム保持性利尿薬なら使用可能です。
β遮断薬は心拍を落ち着かせる働きをします。
β遮断薬は、心拍を落ち着かせて血管を流れる血液量を調節することで血圧を下げます。β遮断薬であるコンコールは、日本ではメインテートと呼ばれています。狭心症や心室性期外収縮などの心疾患の治療にも活用されています。冠攣縮性狭心症を伴う高血圧症患者にはCa拮抗薬との併用が有効です。
心不全、頻脈、狭心症、心筋梗塞後を伴う高血圧症に積極的適応があります。喘息や高度な徐脈がある方は使用しないでください。
食事・運動療法は高血圧症治療の基本
生活習慣の改善は、血圧の下降および降圧薬の作用を増強することが認められています。食事療法・運動療法は薬物療法の開始前のみならず、開始後も続ける意義があります。薬の服用の有無に関係なく、高血圧症治療の基本は食事療法・運動療法です。
高血圧症の治療における生活習慣の修正項目は減塩食・野菜などの摂取・減量・運動・節酒・禁煙です。これらの項目を改善することで血圧の下降が期待できます。
| 減塩食 | 1日6mg未満 |
|---|---|
| 野菜・果物 | 積極的に摂取する |
| 脂質 | コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を抑えて、魚(魚油)を積極的に摂取する |
| 減量 | BMI{体重(kg)-[身長(m)]?}が25未満 |
| 運動 | 有酸素運動を毎日30分以上 |
| 節酒 | エタノールとして1日に男性は20~30mL、女性は10~20mL(エタノール20~30mLは日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本に相当する) |
| 禁煙 | 受動喫煙も避ける |
食事療法では減塩食とDASH食の組み合わせが有効です。
食事療法では、減塩食により昇圧の原因となる食塩の摂取量を抑えます。カリウムやカルシウムなど降圧を助ける栄養を積極的に摂取することで、高血圧症の治療を目指します。
減塩食では、塩分摂取量が1日6mg未満となるようにします。塩分を多く含んでいる練り物や汁物などは避けます。世界的に見て塩分摂取量が多い日本人の高血圧症治療には、減塩食による塩分制限が大切です。
アメリカで行われている高血圧症の食事療法にDASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension)食というものがあります。日本語で高血圧を防ぐ食事療法という意味の略語で、減塩食と組み合わせることで治療効果が高まります。DASH食は、摂取する食べ物を取捨選択して血圧をコントロールする食事療法です。具体的には、カリウムやカルシウム、マグネシウム、水溶性食物繊維、たんぱく質を増やします。一方で飽和脂肪酸やコレステロールを減らします。
- 増やしたい食品
- 野菜、果物、低脂肪乳製品、魚介類、大豆製品、海藻など
- 減らしたい食事
- 肉類、コレステロールが多い食品(レバー、マヨネーズ、たらこなど)
定期的な有酸素運動が血圧を低下させます。
高血圧症の運動療法には、ややきついと思う程度の有酸素運動が有効です。ウォーキングや軽いジョギング、水中運動などの有酸素運動を、週に3〜4回のペースで1日30分程度行うことで降圧が期待できます。可能であれば、毎日運動を続けることが理想です。
有酸素運動のメリットは降圧だけではありません。体重や体脂肪を減らし、血糖値や血清脂質の改善にも有用です。肥満者の高血圧症治療には、減量が効果的です。約4kgの減量により収縮期が-4.5mmHg、拡張期が-3.2mmHgと有意に低下したことが確認されています。

