メトホルミンが配合されている通販商品
メトホルミンの最新ニュース
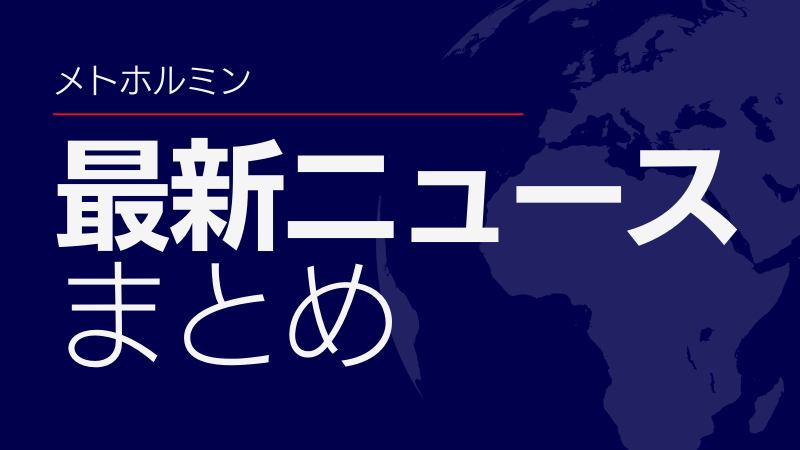
最新研究から明らかになったメトホルミンの驚くべき可能性をお届けします。
老化抑制、がん治療への応用、COPDの病態進行抑制、そしてC型肝炎患者の肝細胞癌リスク低減と、その効果は多岐にわたります。これらの進展は、メトホルミンがただの糖尿病治療薬以上の役割を持つことを示唆しており、医学界に新たな希望をもたらしています。
『メトホルミンによる長寿命化への期待:アンチエイジング効果の新たな可能性』
糖尿病治療薬として広く使用されている「メトホルミン」に、人々の寿命を延ばす可能性があることが注目されています。最新の研究では、メトホルミンが持つアンチエイジング効果に焦点を当て、その寿命延長の効果を確かめる臨床試験が進行中です。
この研究は、メトホルミンが細胞レベルで老化プロセスにどのように作用し、健康寿命を向上させるかを解明することを目指しています。これらの成果が将来の長寿命化や老化防止策の開発につながることが期待されており、医学界だけでなく一般社会にも大きな影響を与える可能性があります。
糖尿病の治療薬として広く利用されている「メトホルミン」に、アンチエイジング(抗加齢)の効果がある――メトホルミンを使い高齢者の寿命を延ばそうという臨床試験が、世界ではじめて米国で今年から行われることになった。
2016年01月14日:「メトホルミン」が寿命を延ばす アンチエイジング効果を確かめる試験 - 糖尿病ネットワーク
『メトホルミン、新型コロナ後遺症リスクを著しく低減―最新研究が示す希望の光』
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う後遺症、いわゆる「新型コロナ後遺症(ロングコビッド)」のリスクを低下させる可能性があるという、画期的な研究結果が発表されました。糖尿病治療薬であるメトホルミンを早期に使用した患者では、新型コロナ後遺症の発症リスクが40%低下し、症状発現から3日以内に治療を開始した場合、その効果は63%にも上ることが明らかになりました。
この結果は、メトホルミンがCOVID-19の急性期に使用されることで、長期にわたる健康問題のリスクを顕著に減少させることを示唆しています。メトホルミンは、安価で広く入手可能な薬剤であり、新型コロナ後遺症の予防におけるその有効性は、世界中の公衆衛生への大きな影響をもたらす可能性があります。これらの発見は、既存の治療薬の新たな応用により、COVID-19とその長期的影響を管理する新しい道を開くことを期待させます。
(翻訳)安価で安全、そして広く入手可能な糖尿病治療薬であるメトホルミンは、新型コロナウイルス感染症の急性期に投与すれば、新型コロナ後遺症の発生率を減少させる可能性があることが、新しい研究で示された。
2023年06月08日:Covid-19: Metformin reduces the risk of developing long term symptoms by 40%, study finds - The BMJ
(翻訳)The Lancet Infectious Diseases誌に発表された新しい研究で、ミネソタ大学の研究者らは、糖尿病治療に一般的に使用される薬剤であるメトホルミンが、新型コロナ後遺症の発症を予防することを発見した。
2023年06月09日:Study Shows Metformin Lowers Long COVID Risk - Newsroom
補足情報:新型コロナ後遺症
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、COVID-19感染後数週間から数ヶ月にわたって続く多様な症状を指し、呼吸困難、慢性疲労、脳霧、不安、ストレスなどを含みます。現在、新型コロナ後遺症の治療法や予防法は確立されていません。
『メトホルミン:がん治療と予防における新たな地平を切り開く』
メトホルミンが、がん治療と予防においても有効である可能性が高まっています。疫学研究によると、メトホルミン使用者は非使用者に比べてがんのリスクが低いことが示されており、この発見はメトホルミンをがん治療薬として再評価する動きを加速させています。
メトホルミンはAMPK活性化作用を通じて、がん細胞のシグナル伝達と代謝に影響を与えることが分かっています。特に、mTORC1の抑制や、がん細胞のミトコンドリア機能への影響を通じて、がんの増殖を抑制する可能性があります。これらの作用メカニズムは、メトホルミンががん細胞の代謝を直接的に変化させることにより、がん治療における新しい治療法の可能性を示唆しています。さらに、メトホルミンは血糖値やインスリンレベルを下げることで、間接的にがんのリスクを低減することも示唆されています。
これらの発見は、メトホルミンが持つがんに対する治療および予防効果の可能性を裏付けるものであり、今後のがん治療におけるメトホルミンの役割について、さらなる研究が期待されています。
(翻訳)疫学的研究により、メトホルミンの使用と癌の予防や治療に対する有益な効果との関連が同定され、抗がん剤としてのメトホルミンの使用の可能性への関心が高まっている
2014年11月06日:Metformin in cancer treatment and prevention - PubMed
(翻訳)メトホルミンの作用機序は、相互に排他的ではない2つの大まかなカテゴリーに分けられる。すなわち、血糖値やインスリン値とは無関係にがん細胞に直接作用する「直接作用」と、血糖値やインスリン値に依存した全身の代謝変化から生じる「間接作用」である。
2016年01月14日:Metformin and cancer hallmarks: shedding new lights on therapeutic repurposing - Journal of Translationa
メトホルミンの禁忌事項
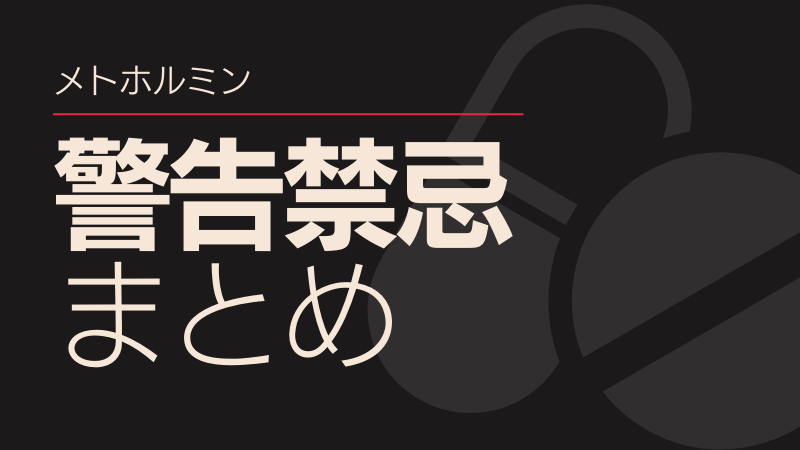
下記に該当する方はメトホルミンを使用しないでください。
- 乳酸アシドーシスを起こしやすい状態にある
- 重症ケトーシス、糖尿病性昏睡または前昏睡、1型糖尿病
- 重症感染症、手術前後、重篤な外傷がある
- 栄養不良状態、飢餓状態、つい弱状態、脳下垂体機能不全、副腎機能不全
- 妊婦
- メトホルミンまたはビグアナイド系薬剤に対して過敏症を起こしたことがある
メトホルミンでは、意識障害や昏睡などの重篤な症状を伴う乳酸アシドーシスの発現が報告されています。乳酸アシドーシスを発症しやすい状態にある方は、メトホルミンを使用できません。
尿酸アシドーシスを起こしやすい患者の例としては以下があります。
- 中等度以上の腎機能障害または腹膜を含む透析患者
- 過去に乳酸アシドーシスを起こした経験がある
- 重度の肝機能障害・ショック
- 心不全
- 心筋梗塞
- 肺塞栓等心血管系・肺機能に高度の障害がある
- 低酸素血症を伴いやすい状態
- 過度にアルコールを摂取している
- 脱水症状および脱水症状が懸念される下痢、嘔吐などの胃腸障害
重症ケトーシスや糖尿病性昏睡または前昏睡、1型糖尿病の患者にはメトホルミンによる治療は適していません。これらに対しては輸液やインスリンによる速やかな高血糖の改善が必要です。重症感染症や手術前後、重篤な外傷がある患者においてもインスリン注射による治療が適しています。また乳酸アシドーシスを起こしやすいとも考えられているため、メトホルミンは使用しません。
栄養不良状態や飢餓状態、衰弱状態、脳下垂体機能不全または腎機能不全の患者は使用できません。メトホルミンの服用によって低血糖を起こすおそれがあります。
メトホルミンは妊娠中に服用した場合の安全性が確認されていません。妊婦または妊娠している可能性がある方は使用しないでください。
メトホルミンあるいはメトホルミンと同様の作用機序を有するビグアナイド系薬剤を使用して過敏症を発現したことがある方は禁忌となります。メトホルミンを使用してしまった場合、重度の過敏症をおこす可能性があります。
メトホルミンの働き
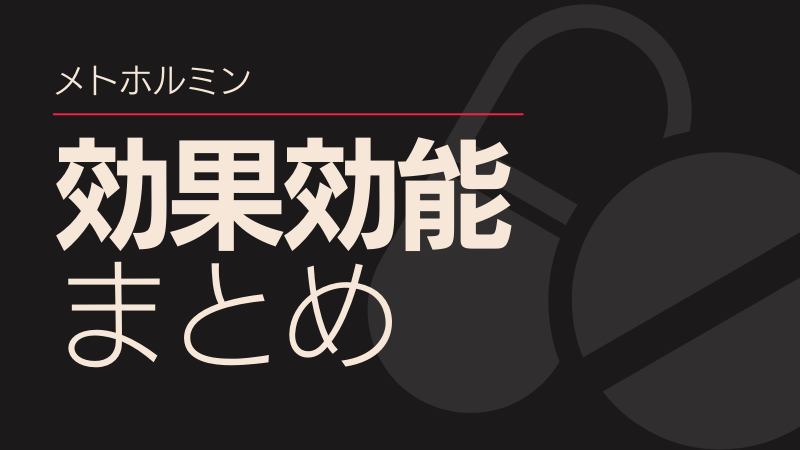
- 効能・効果
- 2型糖尿病
- (1) 食事療法および運動療法で十分な効果が得られなかった場合に有効です。
(2) 経口血糖降下薬もしくはインスリン製剤の服用で十分な効果が得られなかった場合に有効です。
一般名:メトホルミン塩酸塩
2型糖尿病の治療に使われる糖尿病治療剤です。
糖を分解するホルモン(インスリン)の機能を高めます。さらに肝臓での糖新生を抑え、筋肉による糖の消費を促します。複数の効果で2型糖尿病を改善します。
2型糖尿病は、インスリンが減ったり働きが悪くなって血糖値が慢性的に高くなる疾患です。インスリンは、糖をエネルギーに変える重要な働きがあります。メトホルミンは、肝臓から血中に排出されるブドウ糖の量を抑えます。血液中にある糖の消費を高めるため、血糖値の改善に効果的です。
2型糖尿病による高血糖の状態が長期間わたって続くと、血管に大きな負担がかかります。全身のさまざまな臓器に合併症を招くリスクを高めます。血糖値のコントロールをサポートするメトホルミンを活用すれば、2型糖尿病による合併症を予防できます。
メトホルミンは、インスリン分泌量の急激な変化による、低血糖や体重の増加といった悪影響が起こりにくい糖尿病の治療薬として知られています。メトホルミンは分泌後のインスリンの機能を高めて高血糖を改善する薬です。単剤で使用した場合、インスリンの分泌量が急激に変化する心配はありません。
2型糖尿病の薬物療法では、まずメトホルミンに代表されるビグアナイド薬による単剤での治療が行われます。その後の経過によって他の医薬品を追加で使用するという流れが一般的です。
メトホルミンは、糖尿病患者の9割を占めるといわれる2型糖尿病の第一選択薬として世界各国で利用されています。
メトホルミンは2型糖尿病治療薬だけに留まらず、その効果はダイエットにも及びます。インスリン感受性の向上と血糖値の低下を通じて、体重管理に貢献することが期待されています。特に糖尿病患者において、体重減少の副次的な利益が見られることがあり、健康的な生活習慣と組み合わせることで、より効果的なダイエットサポートが可能になる場合があります。個人差はありますが、メトホルミンの使用が新たな体重管理の選択肢として注目されています。
メトホルミンは糖の生成抑制と糖利用の促進から血糖値を改善します。
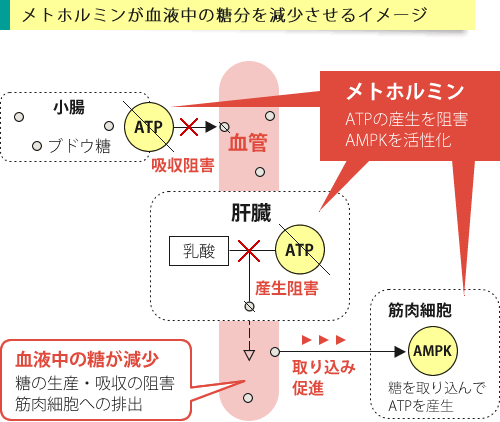
メトホルミンは、アデノシン三リン酸(ATP)を生成する細胞の働きを阻害します。ATPは糖新生などに利用されるエネルギー源です。
メトホルミンの働きによってATPの供給量が減少すると、AMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)という酵素が活性化します。AMPKの活性化は、血糖値の改善に必要なさまざまな働きに関わっています。中性脂肪を減らし、肝臓での糖新生を抑えて血中から糖の代謝を促します。
AMPKの活性化により肝臓に蓄積した中性脂肪の量が減ると、ブドウ糖を分解するインスリンの機能が高まります。さらに肝臓におけるブドウ糖の新生が抑えられます。同時に血中から筋肉や脂肪組織へのブドウ糖の取り込みも促されます。こうしたメトホルミンの働きをキッカケにおこる体内の変化によって、血糖値は効率よく改善されます。
臨床成績においてメトホルミンは合併症の発生リスクを有意に低下させました。
血糖値を改善するメトホルミンの効果は、2型糖尿病患者を対象とした54週間にわたる臨床試験*において実証されています。食事療法と運動療法、もしくはこれらに加えてスルホニルウレア剤を内服して効果が十分でない患者に、メトホルミンが投与されました。スルホニルウレア剤は肝臓からインスリン分泌を促す薬です。
メトホルミンの継続投与によって、患者のHbA1c値が下がり、多くの割合で合併症のリスクが少ないとされる水準まで改善しました。
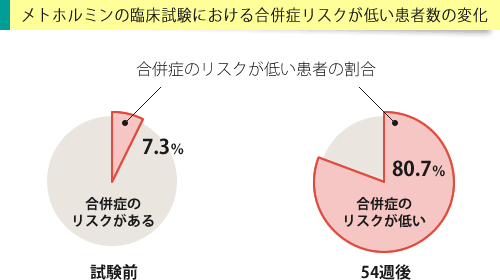
臨床試験前には合併症のリスクが低い患者の割合は7.3%でした。
メトホルミンを1日2〜3回投与し続けた結果、合併症のリスクが低い患者の割合は増えていきました。14週後で65.4%、26週後に73.5%、54週後には80.7%でした。
臨床試験の期間中は1日500mgからメトホルミンの服用を開始しました。患者の状態に応じて750〜2250mgの間で用量の調節が行われています。メトホルミンを投与した患者の大半に血糖値の改善が認められました。これにより、2型糖尿病に対する効果が実証されました。
※出典:リンク先、販売名:メトグルコ錠250mg/メトグルコ錠500mgのインタビューフォームを参照
メトグルコを先発薬とした糖尿病の治療薬の有効成分として配合されています。
- メトホルミンが配合されている糖尿病の治療薬
- 先発薬:メトグルコ(メルク・サンテ)
- 後発薬:メトホル(シプラ)
メトホルミンの副作用
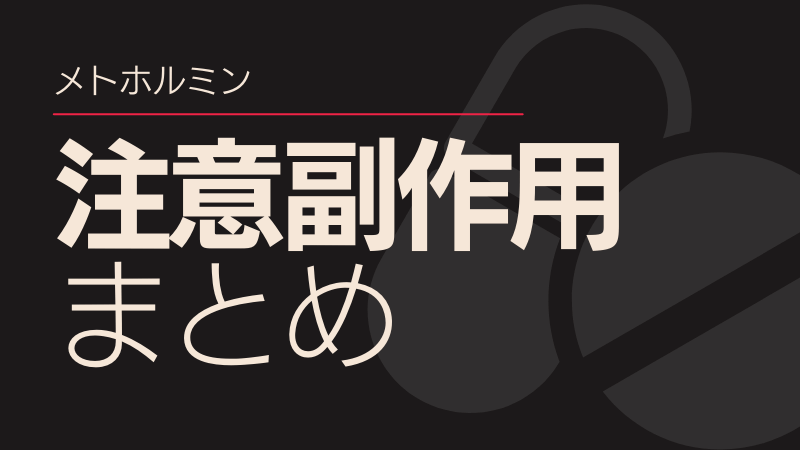
副作用
全身倦怠感、頭痛、頭重、眠気、肝機能異常、食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢、便秘、消化不良、腹痛、腹部膨満感、過敏症(発疹)などが生じることがあります。
重大な副作用
低血糖、乳酸アシドーシス、肝機能障害、黄疸、横紋筋融解症、類天疱瘡。
以下はメトグルコ錠のインタビューフォーム*に記載されていた副作用の発現率です。
| 副作用の症状 | 発現数 | 発現率 |
|---|---|---|
| 下痢 | 262例 | 40.9% |
| 悪心 | 97例 | 15.2% |
| 食欲減退 | 80例 | 12.5% |
| 腹痛 | 67例 | 10.5% |
| 低血糖 | 44例 | 6.9% |
| 血中乳酸増加 | 36例 | 5.6% |
メトホルミンの主な副作用は、食欲不振や便秘、下痢、吐き気などの胃腸症状です。これらの副作用は軽度であるケースが大半です。ただし脱水症状につながることもあるため、注意が必要です。ふるえや寒気、強い空腹感、動悸などの症状は低血糖の可能性があります。低血糖には糖分を補給することで対処できます。
非常に低い頻度ではありますが、メトホルミンの副作用として乳酸アシドーシスが報告されています。乳酸アシドーシスは胃腸症状や倦怠感、過呼吸、筋肉痛の症状が現れることが多くあります。これらの症状が確認された場合、すぐに服用を中止して医師の診察を受けてください。
- 使用に注意が必要な人
- <不規則な食事摂取、食事摂取量の不足がある>
食物の吸収不良が生じて、低血糖となる可能性があります。 - <激しい筋肉運動>
メトホルミンにより腸内ガスが増加して、腸閉塞を生じることがあります。 - <軽度の腎機能障害がある>
メトホルミンの排泄が遅延して血中濃度の上昇がみられることがあります。乳酸アシドーシスを起こすおそれがあるので注意してください。 - <軽度~中等度の肝機能障害がある>
肝臓では乳酸の代謝が行われます。上記の患者では肝臓における乳酸の代謝機能が低下しています。乳酸値が上がりやすく乳酸アシドーシスを生じるおそれがあります。 - <感染症に罹患している>
インフルエンザや急性肺炎、急性腸炎などの重い感染症ではメトホルミンを使用してはいけません。脱水による乳酸アシドーシスが生じるリスクが高くなります。症状が軽度の場合でも、十分に病状を観察しながら慎重に使用する必要があります。 - <高齢者>
腎機能や肝機能などが低下していることが多い高齢者は、脱水症状を起こしやすくなります。メトホルミンを使った際の乳酸アシドーシスの出現リスクが高いと考えられます。特に75歳以上の高齢者には乳酸アシドーシスが多く報告されています。
- 併用注意薬
- <尿酸アシドーシスの起因となる薬>
ヨード造影剤、ゲンタマイシン、利尿剤、SGLT2阻害剤など。
ヨード造影剤やゲンタマイシンなどの腎毒性の強い抗生物質を服用している方は、腎機能が低下していると考えられます。メトホルミンとの併用により尿酸アシドーシスを起こすことがあります。利尿剤やSGLT2阻害剤などの利尿作用を有する薬剤では、脱水状態による尿酸アシドーシスに注意が必要です。 - <血糖降下作用を増強する薬>
糖尿病治療薬、たん白同化ホルモン剤、サリチル酸剤、β遮断薬、モノアミン酸化酵素阻害剤。
メトホルミンとの併用時に低血糖を起こすことがあります。低血糖がみられた際にはショ糖(砂糖)を摂取してください。アカルボースなどのα-グルコシダーゼ阻害剤と併用している場合には、ブドウ糖を摂取してください。 - <血糖降下作用を減弱する薬>
アドレナリン、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、卵胞ホルモン、利尿剤、ピラジナミド、イソニアジド、ニコチン酸、フェノチアジン系薬剤。
メトホルミンの血糖降下作用が弱まることがあります。体の状態を観察しながら服用してください。 - <シメチジン、ドルテグラビル、バンデタニブ>
上記の薬剤がメトホルミンの排泄を阻害することで、血中濃度が上昇して作用が必要以上に強く現われることがあります。メトホルミンの用量を減らすなどして慎重に使用してください。
- メトホルミンと関連する成分
- アカルボース
α-グルコシダーゼという酵素と結びつき、食後過血糖を改善する2型糖尿病の治療薬です。動脈硬化や腎障害といった合併症を予防するほか、肥満体質の改善にも効果的です。





