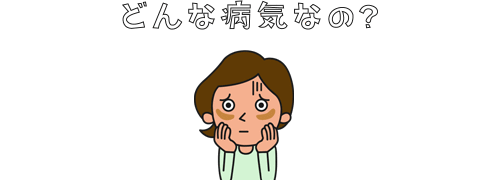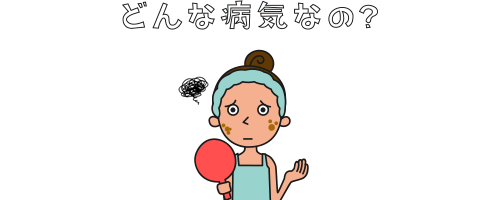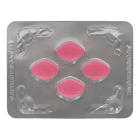トラネキサム酸が配合されている通販商品
トラネキサム酸の禁忌事項
下記に該当する方はトラネキサム酸を使用しないでください。
- トロンビンを使用中
トラネキサム酸とトロンビンを併用した場合、血栓症を招く危険があります。トロンビンは、消化管出血の治療に使われる止血剤です。トロンビンとトラネキサム酸を同時に使用すると、血液を固める作用が増強されるため、血栓が生じやすくなります。
トラネキサム酸の働きと効果
- 効能・効果
- 老人性色素斑、肝斑、雀卵斑、摩擦黒皮症、炎症後色素沈着
- (1) 老化や紫外線、ニキビ跡でできるシミを薄くします。
一般名:トラネキサム酸
老人性色素斑などのシミ、肝斑の治療に使われる止血剤です。
左右対称に淡いシミが現われる肝斑を改善する効果があります。肝斑の原因は、女性ホルモンのバランスの乱れに起因するメラノサイトの活性化です。メラニン色素の生成が増加して頬骨や額、口の周辺に沈着することでシミが現われます。トラネキサム酸は、シミの原因となるメラニンの過剰な生成を抑制することで肝斑の症状を改善します。
トラネキサム酸は、シミや肝斑の治療を行うのと同時に新たな色素沈着を予防する働きもあります。もともと止血剤として開発されたトラネキサム酸には、抗炎症作用や抗アレルギー作用もあります。
色素沈着の原因は紫外線や炎症などによる肌への刺激です。トラネキサム酸には刺激の1つである炎症を鎮める効果が期待できます。実際に湿疹や蕁麻疹に伴う腫れを抑えるためにトラネキサム酸が処方されることもあります。
トラネキサム酸は、1962年に日本で開発された抗プラスミン薬です。止血剤として利用されている中で肝斑の改善が確認されたため、肝斑の治療薬として使われるようになりました。副作用の発現率も非常に低く、安全性にも優れた成分です。白く美しい肌をつくる美白効果があり、世界各国で利用されてきたトラネキサム酸は、WHOが制作した必須医薬品リストにも記載されている成分です。
トラネキサム酸がメラノサイト活性物質を阻害します。
トラネキサム酸は、抗プラスミン作用によってメラニン色素の産生を抑制します。プラスミンとは、メラノサイト(メラニンを生成する細胞)を活性化させる働きのある情報伝達物質です。トラネキサム酸は、前駆物質であるプラスミノーゲンからプラスミンへの変換を阻害します。プラスミンが作られなくなることで、メラノサイトの働きが抑えられて、メラニン色素の分泌が減少します。
トラネキサム酸には、炎症発生時に生じる血管透過性の亢進に伴う組織の腫脹を抑えます。アレルギーや炎症性病変を引き起こすキニンやその他の活性ペプタイドなどの物質の産生を抑制する働きもあります。
トラネキサム酸の臨床成績では89.7%の肝斑を薄くすることに成功しました。
シミや肝斑を改善するトラネキサム酸の効果は、顔に左右対称のシミを有する561名を対象に実施された臨床試験で実証されています。臨床試験は、トラネキサム酸錠を1日2〜3回服用し、4ヶ月のあいだ経過を観察してシミや肝斑の症状の改善率を検証する方法で行われました。
臨床試験の結果、561名のうち89.7%にあたる503名に対して症状の改善(シミが薄くなる)が確認されました。臨床成績から、シミや肝斑の治療におけるトラネキサム酸の有用性が証明されました。
トラネキサム酸を配合したシミ・肝斑を消す薬としては「パウゼ」が挙げられます。
トラネキサム酸の副作用
副作用
食欲不振、吐き気、嘔吐、下痢、胸やけなどが生じることがあります。
重大な副作用
けいれん。
| 副作用の症状 | 発現数 | 発現率 |
|---|---|---|
| 食欲不振 | 18例 | 0.61% |
| 悪心 | 12例 | 0.41% |
| 嘔吐 | 6例 | 0.20% |
| 胸やけ | 5例 | 0.17% |
| 痒み | 2例 | 0.07% |
| 発疹 | 2例 | 0.07% |
トラネキサム酸の主な副作用は、食欲不振や悪心、嘔吐などの消化器系の症状です。決して副作用の強い薬ではありませんが、異常を感じた場合には服用を中止して医師に相談してください。
その他の副作用としては、痒みや発疹、眠気などの症状が報告されています。いずれも0.1%未満のきわめて低頻度となっています。
重大な副作用としては、けいれんが報告されています。報告されたのは人工透析を行っている患者であり、健康な成人が使用する場合には過度に気にする必要はありません。
※出典:第一三共株式会社. (2015). トランサミン錠250・500mg/トランサミンカプセル250mg/トランサミン散50%.(PDF:374KB)
- 使用に注意が必要な人
- <血栓のある患者および血栓症のおそれのある患者>
脳血栓や心筋梗塞、血栓性静脈炎などの血栓を有する方では、トラネキサム酸が症状を増悪させる可能性があります。高脂血症や動脈瘤など血栓症が生じる素因を有する方も注意が必要です。 - <消費性凝固障害のある患者>
上記疾患に該当する場合、血栓が生じやすくなります。トラネキサム酸とヘパリンなどの抗凝固剤を併用して、血液の凝固系を抑制する必要があります。 - <手術後床にふせった状態または圧迫止血の処置を受けている患者>
上記に該当する方では、静脈血栓が生じやすくなっています。トラネキサム酸が投与された患者では、離床もしくは圧迫解除に伴って肺塞栓症を発症した例が報告されています。 - <腎不全のある患者>
上記疾患に該当する場合、通常よりもトラネキサム酸の血中濃度が上昇する可能性があります。腎臓から排泄されるトラネキサム酸は、腎機能の低下している方では血中からの消失が遅延する可能性があります。 - <トラネキサム酸に対して過敏症を起こしたことがある>
以前にトラネキサム酸を使用した際にかゆみや発疹などの過敏症が出た経験のある方は、再び過敏症状が出る可能性が高くなります。
- 併用注意薬
- <ヘモコアグラーゼ>
内科や外科婦人科、耳鼻科などで幅広く使われている止血薬です。トラネキサム酸との併用によって血栓が生じやすくなります。 - <バトロキソビン>
突発性難聴や慢性動脈閉塞症の治療に使われます。トラネキサム酸との併用によって血栓・塞栓症を生じるおそれがあります。 - <凝固因子製剤>
エプタコグ アルファなど。
血友病などの治療に使われます。口腔の手術で併用する場合、血液凝固作用が過度に増強するおそれがあります。