セチリジンが配合されている通販商品
セチリジンの禁忌事項
下記に該当する方はセチリジンを使用しないでください。
- セチリジンまたはピペラジン誘導体に対して過敏症を起こしたことがある
- 重度の腎障害がある
セチリジンに対して発疹や喉や顔の腫れ、ショックなどの過敏症が出たことのある方は使用できません。セチリジンが含まれるピペラジン誘導体に分類される薬剤に対して、過敏症の既往がある方も同様です。ピペラジン誘導体にはその他にも、レボセチリジンやヒドロキシジンなど様々な種類の薬が含まれています。
腎障害のある方がセチリジンを摂取すると、過度に高い血中濃度が維持されるおそれがあります。腎機能が正常な方と比較すると、血中濃度半減期が約1.1~3.1倍に延長したと報告されています。腎機能検査値のクレアチニンクリアランスが10mL/min未満である重い腎障害を抱える方はセチリジンを使用できません。
セチリジンの働きと効果
- 効能・効果
- アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹、皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症)
- (1) 花粉症など季節性の鼻炎および通年性のアレルギー性鼻炎の症状緩和に有効です。
(2) 蕁麻疹、湿疹や皮膚炎などの皮膚疾患の症状を和らげます。
一般名:セチリジン塩酸塩
花粉症や蕁麻疹などアレルギー症状の治療に使われるアレルギー性疾患治療剤です。
アレルギー症状の原因となるヒスタミンなどの情報を伝達する物質の遊離や働きに作用し、かゆみやくしゃみ、鼻水、蕁麻疹などさまざまなアレルギー反応を抑え込みます。
花粉症や蕁麻疹といったアレルギー性の症状は、ヒスタミンが対応した受容体と結合することで起こります。
ヒスタミンは細菌やウイルスなどの異物の侵入を防ぐために必要な免疫機能の1つです。免疫機能が花粉やほこりなど体に無害な異物に対して過剰に反応することがあります。この過剰な反応で引き起こされるのが花粉症や蕁麻疹などのアレルギー症状です。
セチリジンは、これらのアレルギー反応を強力に抑える効き目に優れており、作用には持続性があります。
セチリジンは1986年にベルギーで初めて承認を受けました。承認から30年以上が経過しており、現在ではセチリジンを利用している国は世界100ヵ国を超えています。長期にわたり多くの花粉症や蕁麻疹などアレルギー症状に悩む患者に使われてきました。
セチリジンは情報伝達物質の遊離とヒスタミンの受容体結合を抑制します。
セチリジンの作用は、免疫機能の誤作動を引き起こすヒスタミンなどのケミカルメディエーターという体内で情報を伝達する役割を持つ物質の遊離や働きを抑制することにあります。セチリジンが体内に吸収されると、ヒスタミンを含むケミカルメディエーターの遊離抑制、ヒスタミンの結合阻害という2つの作用を発揮します。
異物が体内に侵入すると免疫に関係する細胞からヒスタミンを含むケミカルメディエーターが遊離して、受容体と結合しアレルギー反応を引き起こします。セチリジンが体内に取り込まれると1つ目の作用がヒスタミンやその他のケミカルメディエーターが細胞から離れるのを抑制します。そして2つ目の作用がヒスタミンH1受容体に作用することで、すでに遊離したヒスタミンの働きを抑制します。セチリジンはこの2つの作用によってヒスタミンの働きを抑えます。異物の侵入で起きた免疫の誤動作を解消して、花粉症や蕁麻疹などのアレルギー反応を強力に抑制します。
セチリジンは臨床試験においてアレルギー性鼻炎への有用性を示しています。
セチリジンのアレルギー症状に対する有効性は、ジルテックの臨床試験*からわかります。通年性アレルギー性鼻炎を発症した患者を対象とした臨床試験が行われました。セチリジン10mgを1日1回のペースで服用した場合、2週間で53.8%(21/39例)の患者で中等度以上の改善が確認されました。
臨床試験の結果から、花粉症を含むアレルギー性鼻炎に対するセチリジンの有効性が高いことがわかりました。
※出典:リンク先、販売名:ジルテック錠5/ジルテック錠10のインタビューフォームを参照
セチリジンは、ジルテックを先発薬とした花粉症・鼻炎の治療薬の有効成分として配合されています。
- セチリジンが配合されている花粉症・鼻炎の治療薬
- 先発薬:ジルテック(UCB)
花粉症の薬を効き目の強さで比較

第二世代の抗ヒスタミン薬を効き目が強い順でランキングを作成。病院の処方薬や市販薬を含めた最強の薬を決定!
花粉症の薬を眠くなりにくさで比較
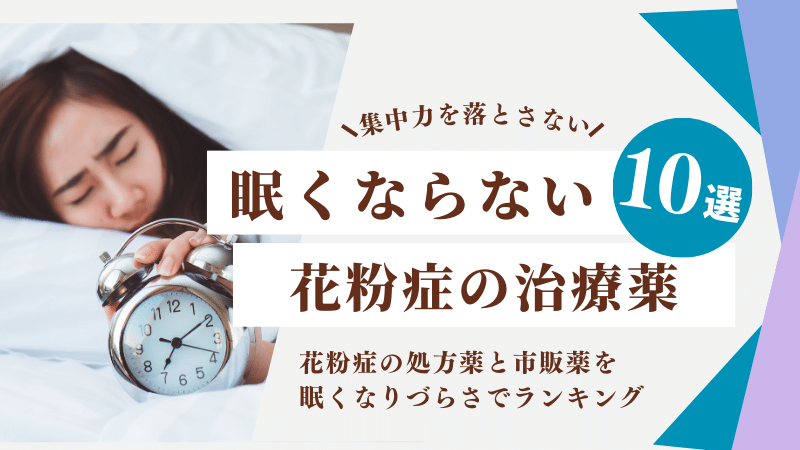
花粉症の薬を眠くなりづらさでランキングを作成。車の運転中や試験勉強中でも安心して服用できる花粉症の薬を紹介。
セチリジンの副作用
副作用
眠気、倦怠感、口の渇き、吐き気、胃部不快感、消化不良、腹痛、胃痛、腹部不快感、頭痛、しびれ感、動悸、むくみ、胸痛などが生じることがあります。
重大な副作用
けいれん、肝機能障害、ショック、アナフィラキシー様症状、血小板減少。
以下はジルテックのインタビューフォーム*に記載されていた副作用の発現率です。
| 副作用の症状 | 発現率 |
|---|---|
| 傾眠 | 6.02% |
| ALT増加 | 1.52% |
| AST増加 | 1.44% |
| 倦怠感 | 0.86% |
| 好酸球数増加 | 0.81% |
| 口渇 | 0.64% |
セチリジンで最も多く確認されている副作用は、眠気(傾眠)です。ヒスタミンは脳の活性にも関わりのある成分であるため、働きを抑制すると眠気が発生しやすくなります。
第二世代に分類されるセチリジンは、第一世代の抗ヒスタミン薬と比べて眠気の発現が大幅に低下していますが、発現には注意が必要です。セチリジンの服用後は、車の運転など機器の操作や高所での作業は控えてください。眠気以外では、倦怠感や口の渇き、吐き気などの副作用が確認されています。
- 使用に注意が必要な人
- <腎障害のある患者>
上記疾患に該当する場合、腎機能正常者と比較して血中濃度が高いまま持続する可能性があります。重症の腎障害のある方に対しては禁忌とされていることから、事前に検査を受けて医師に使用の可否を問う必要があります。 - <肝障害のある患者>
上記疾患に該当する場合でも、高い血中濃度が持続するおそれがあります。原発性胆汁性肝硬変やアルコール性肝硬変などの肝障害がある患者を対象とした試験では、血中濃度減少の遅延が確認されています。高度の肝障害がある方では、医師による投与量の調整が必要となります。 - <高齢者>
高齢者でも同様に医師による投与量の調整が必要となります。セチリジンは主に腎臓から排泄されます。腎機能が低下している方が多高齢者では、血中濃度が過度に高い値で持続するおそれがあります。 - <痙攣性疾患の患者または既往歴がある>
てんかんなどの痙攣(けいれん)性疾患を有する方では、痙攣や発作の発現が助長されるおそれがあります。セチリジンのようなヒスタミンH1受容体拮抗作用を有する薬は中枢神経を刺激する作用があるため、てんかん患者や痙攣の危険性が高い患者には慎重な投与が望ましいとされています。
- 併用注意薬
- <テオフィリン>
気管支喘息や慢性気管支炎などに使われます。詳しい機序は不明とされていますが、体内からのセチリジンの排泄が妨げられます。 - <リトナビル>
HIV感染症治療に用いられます。併用時にセチリジンの取り込まれる量(曝露量)が40%増加し、反対にリトナビルでは11%減少したという報告があります。 - <中枢神経抑制剤、アルコール>
不眠症治療や麻酔、けいれん発作の抑制などさまざまな用途で使われます。セチリジンを併用した際に、中神経抑制作用が増強される可能性があります。 - <ピルシカイニド塩酸塩水和物>
頻脈性不整脈を治療します。併用により両剤の血中濃度が上昇するおそれがあります。血中濃度の過度な上昇は、副作用の発生リスクを高めます。
- セチリジンと関連する成分
- フェキソフェナジン
アレルギー性鼻炎や蕁麻疹、アトピー性皮膚炎などの治療に用いる抗ヒスタミン薬です。花粉症の発症予防に適しており、眠気などの副作用が少ないことも特徴です。 - レボセチリジン
セチリジンの効き目の強さはそのままに眠気の副作用が起こりにくくなるよう改良された成分です。発症してしまった花粉症の鼻炎などの症状を強力に抑える効果に優れています。 - ロラタジン
穏やかな効き目が長時間続く抗ヒスタミン薬です。花粉症の薬の服用中によくある眠気の副作用が最も起こりづらい特性があり、眠くならないアレルギー性鼻炎の薬として重宝されています。 - オロパタジン
オロパタジンは、花粉症やアレルギー性鼻炎の症状緩和に使用される、抗ヒスタミン薬です。くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどを軽減します。花粉症の治療薬の中でも、特に即効性の高さや効果の優位性に特徴があります。


